すすきとお団子を飾って月を鑑賞する、日本のゆとりある風習「お月見」。
鏡のように輝く大きな黄色い月は、見れば見るほど神秘的で物語が生まれてきそうですね。
ここでは、お月見の由来や今年の日程、十五夜との関係などもご紹介していきます。
お月見とは?

夜空に黄金の光を放つ月。その姿が最も輝くといわれる旧暦八月十五日の夜――
それが「十五夜」、別名 中秋の名月 です。
まるで天からの祝福のように澄み渡る光に包まれたこの夜、人々は古来より、月に心を寄せてきました。
縁側や庭先には、風に揺れるすすきが飾られ、手作りの月見団子や旬の野菜・果実がお供えされます。
それはただのもてなしではなく、大地の恵みへの感謝と、これから訪れる実りの季節への祈りを込めた儀式です。
やわらかな月光に照らされながら、静かに空を仰ぐと――そこには、時を超えて日本人の心を結び続けてきた「秋の宴」が広がります。
お月見とは、単なる月を見ることではなく、自然と共に生きる喜びを確かめ、明日への希望を託す、豊饒で幻想的なひとときなのです。
お月見の由来
お月見をする目的は、大きく2つに分けるられます。
ひとつは、月の美しさを愛でてその風情を楽しむための「観賞としてのお月見」。
もうひとつは、秋の実りに感謝し、豊穣を祈る「信仰・祈願としてのお月見」です。
この行事は、外から伝わった文化と日本固有の風習が重なり合い、時代の流れの中で姿を変えながら根付いてきました。
その歴史をたどりながら、お月見がどのように人々の暮らしや心に寄り添ってきたかをご紹介します。
平安時代に日本へ
旧暦八月十五日――「十五夜」の名月を愛でる風習は、遥か唐の都(中国の首都)で生まれました。その輝きは海を越えて伝わり、平安の世に花ひらきます。
月を仰ぎ、歌を詠み、酒を傾ける。宮中に響くのは雅やかな詩歌の声。
満月の光に照らされ、雅宴を執り行ったのは村上天皇でした。
その姿を手本に、やがて都の貴族たちの間にも、この風流なお月見が広がっていきます。
彼らが見つめたのは、空高く輝く月だけではありません。
水面にゆらめく月影、盃に宿る黄金の光――あらゆる景色の中に月を探し、その美を堪能しました。
舟を浮かべ、波間に映る月を友として詩を紡ぎ出す、贅を尽くした雅の遊び。
かつての人々は、「十五夜」の月に心を重ねながら、物語や歌を生み出し、この国の文化に永遠の輝きを刻んでいったのです。
庶民に広がったのは室町時代
やがて時は流れ、月をただ愛でる遊びから――月そのものを「神」と崇める風習へと、お月見は姿を変えていきました。
それが定着したのは室町時代のことと伝えられています。
暦がまだ行き渡らぬ時代、人々は月の満ち欠けを暦代わりにし、種をまく日や収穫の時を定めてきました。
夜空に浮かぶ光は、ただの自然現象ではなく、暮らしを導く存在。そこに畏敬の念を抱くのは必然でした。
とりわけ、欠けることのない丸い十五夜の月は、大地の豊穣を映す象徴。
人々はその光に感謝を込め、里芋や枝豆、栗や柿、瓜や茄子におかゆなど、秋の恵みを捧げて祈りました。
さらに、萩の箸で茄子に穴をあけ、そこから満月をのぞきながら「月々に月見る月は多けれど、月見る月はこの月の月」と唱える――そんな洒落がかった遊びの中にも、月を畏れ敬う心が込められていました。
目が良くなる、という言い伝えもまた、人々の思いを彩ります。
江戸時代には行楽イベントに
室町の世においては静かな宗教儀式であったお月見――。
しかし時が移り、江戸の世となり安寧が訪れると、それは「秋の大イベント」へと姿を変え、人々の心を弾ませる風習となりました。
夏の熱気がやわらぎ、涼風が吹きわたる頃。人々はこぞって外に繰り出し、澄んだ秋空と黄金の月明かりに酔いしれます。
江戸の町にはお月見名所が点在し、山や社、そして何より海辺が人気を集めました。
水面に揺れて映る月の光――それはまさに日本人の美意識を映し出す、幽玄の世界。
海辺には数多の屋台が立ち並び、香ばしい匂いと人々の笑い声が夜を彩ります。
沖には月見船が浮かび、波間に漂う船上から仰ぎ見る月の美しさに人々は心を奪われました。
さらには夜空に花火が打ち上げられ、天に輝く月と地上の光景が響き合い、まるで夢のような饗宴が広がっていったのです。
江戸の十五夜――それはただ月を仰ぐだけでなく、人々が人生の喜びと美を分かち合う、華やかでドラマティックな祝祭の夜でした。
そして現代へ
かつて宮中で華やかに催されたお月見は、時を経た今、自然を想い、秋を慈しむしとやかな行事へと姿を変えました。
しかし、その風習を今も積極的に祝う人は少なくなり、静かな月の夜を心待ちにする光景は昔ほど見られなくなっています。
お月見には、クリスマスや正月のように人々を浮き立たせる華やかさはありません。
だからこそ、忙しさの中でふと気づけば、十五夜は静かに過ぎ去っていた――そんなことも珍しくありません。
けれども、子どもたちの澄んだ声にのせて「でたでた月が」「うさぎうさぎ」といった歌が響けば、その瞬間、月の伝統は確かに今へと生きています。
だからこそ、私たちはもう一度、この美しい日本の風習に目を向けてみませんか?
澄んだ夜空に浮かぶ名月は、静かでありながら、心を豊かに照らし出す力を秘めているのです。
2025年のお月見はいつ?

それでは気になる「十五夜」とは、いつのことでしょうか。
2025年の十五夜は 10月6日(月) にあたります。
そして、本当の満月となるのはその翌日、10月7日(火) です。
「十五夜=満月」と思われがちですが、実際には十五夜と満月がずれる年がほとんどです。
その理由は、月が完全な円軌道ではなく楕円の軌道を描いていること、そして旧暦の仕組みによる一年の日数の違いにあります。
とはいえ、十五夜の夜に見られるのは「ほんのわずかに欠けた月」。
その姿は、“ほぼ満月”だからこそ味わえる趣があり、古来より人々に親しまれてきました。
なお、十五夜と満月が珍しく重なるのは2030年。
まんまるの十五夜を拝めるその特別な夜を、今から心待ちにしてもよいかもしれませんね!
2024年の十五夜はこのような感じでした。
十五夜の頃はちょうど秋雨前線の影響を受けやすく、天気がすぐれない年も多いのですが、昨年は幸運にも全国的に晴れ間が広がりました。
関東・東海の一部では一時的に雨となったところもありましたが、夜には回復し、雲の切れ間から中秋の名月を望むことができたようです。
結果として、全国各地で夜空にぽっかりと浮かぶ丸い月を仰ぎ見ることができ、まさに「十五夜らしい」ひとときとなりました。
十五夜は毎年日にちが違う

旧暦の8月15日を「十五夜」と呼びます。
そのため「十五夜=毎年9月15日」と思う方も多いのですが、実はそうではありません。
旧暦は月の満ち欠けを基に1か月を約29.5日で数える暦なので、新暦(太陽の動きを基準にした現在の暦)とは日数が異なりズレが生じます。
その結果、十五夜は現在、毎年9月中旬から10月上旬の間に変動して迎えられるのです。
簡単に言えば、旧暦は1年が約354日で、新暦の365日より約11日短いため、この差が積み重なって毎年日付がずれるのです。
さらに、数年ごとに「うるう月(閏月)」が入り調整されるため、十五夜の日付は年によって大きく変わります。
だからこそ十五夜は「毎年決まった日ではない」ということを覚えておくとわかりやすいでしょう。
この仕組みが、歴史あるお月見の奥深さでもあります。
2025年は10月6日。
それ以降の年は、このようになっています。
| 年 | 十五夜 | 満月 |
|---|---|---|
| 2026年 | 9月25日 | 9月27日 01時49分 |
| 2027年 | 9月15日 | 9月16日 08時03分 |
| 2028年 | 10月3日 | 10月4日 01時25分 |
| 2029年 | 9月22日 | 9月23日 01時29分 |
| 2030年 | 9月12日 | 9月12日 06時18分 |
お月見の正しいやり方
テレビアニメ「サザエさん」で描かれるように、月が美しく見える縁側にすすきや月見団子をそっと飾り、月明かりの下で晩ご飯をいただく――そんな風景は、日本の心が伝わる風流なひとときです。
縁側のある家ならば理想的ですが、たとえなくても大丈夫。
自分の家で一番月がよく見える窓辺に、小さな机を置くだけでベランダ越しのお月見が叶います。
さらに庭先にお供え物を並べて、秋の風に吹かれながら静かに満ちゆく月を眺めれば、それもまた風情あるお月見の形です。
この秋は、正しいお月見の作法を知りながら、自然の営みを感じる日本の伝統行事に心を寄せてみませんか。
きっと五感に沁みる、特別な時間が訪れることでしょう。
月見台を決める

まずは、どこで月を愛でるか、その「月見台」を決めましょう。
月見台とは、お月見を楽しむために選ばれた特別な場所のこと。
月の光を存分に感じられる場所があれば、そこがあなたの月見台です。
そこにすすきや月見団子、秋の収穫物を丁寧に飾りつけ、静かな宵に月を仰ぎましょう。
例えば、縁側や庭先、あるいはベランダの角、どこでも構いません。
そこが小さな舞台となり、あなたと満ちゆく月との対話の場となるのです。
ここでいくつかの月見台の例をご紹介しましょう。
| 月見台の例 | 飾り方の一例 |
|---|---|
| 窓辺 | 窓際に小さなテーブルを置いてお供え物を飾る |
| 出窓 | 出窓の張り出し部分を利用してお月見飾りをする |
| 庭 | 庭にガーデンテーブルなどを設けて飾る |
| ベランダ | ベランダにテーブルを出して月を眺める |
| 縁側 | 縁側にちゃぶ台を置いて風流に飾る |
どの場所でも、すすきや旬の収穫物、月見団子を丁寧に飾り付けて、静かな夜空の月を楽しむことができます。
部屋の明かりを控えめにして、月の光をより美しく感じられるようにするのもおすすめです。
お供え物をする
出典;http://kodaira-furusatomura.jp
お月見をするときの正式なお供え物と飾り方は以下の通りです。
- お供えするものは、三方(木製の四角い台)の上に月見団子、里芋、枝豆、季節の果物を盛り、さらに秋の七草を添えます。
- 七草が揃わない場合でも、すすきだけは必ず飾るようにしましょう。すすきは稲穂の代わりであり、魔よけの意味も持っています。
- 月見団子の正式な供え方は三方の上にのせることですが、三方がない場合はお皿に半紙を敷いてお供えしてもかまいません。
- 団子の数は十五夜にちなんで15個を用いるのが一般的で、並べ方は下から9個、その上に4個、さらにその上に2個とピラミッド形に積み上げます。
このように、お供え物には豊作への感謝や健康・幸福を願う意味が込められています。
お月見の夜は、これらの飾りを整えて静かに月を愛でるのが伝統的な楽しみ方です。
月を眺める

お供えして月に感謝を捧げたあとは、ゆったりと月を見上げながら月見団子を味わいましょう。
お月見でお供えした食べ物をいただくことは、月からの恩恵と感謝が返ってくるとされる神聖な行為です。
お月見とは、単なる季節の行事以上のもので、日常の喧騒を離れてしみじみと季節の移ろいを感じ、豊かな時間を味わえる特別な豊かさの証です。
自然と一体となり、自分自身を取り戻せる数少ない日本の伝統文化のひとつなのです。
どうぞ、この秋の長い夜を、静かに月光に包まれながら、心ゆくまでお楽しみください。
お月見のお供え物の意味とは?
お月見で欠かせないお供え物ですが、それぞれどんな意味があるのでしょうか。
月見団子の意味

月見団子は、中国の「月餅」に習ったもので、その丸い形は満ちる満月を象徴しています。
日本では、万葉集の時代から月は欠けては満ちる不死と復活の象徴とされ、丸い団子を食べることで健康と幸せを願う風習が根付いてきました。
ただし、月見団子の形やスタイルは地域によって異なり、それが話題となったこともあります。
出典;http://cosodachi.com
静岡県では中央にくぼみをつけた「ヘソモチ」、関西では里芋に似せた細長い団子にあんこを巻いたものが一般的です。
江戸時代には、野球ボールほどの巨大な月見団子を15個も三方に積み上げるという豪快な風習がありました。
なぜそんなに大きかったのか?今も謎のままですが、当時の月見がいかに盛大であったかを物語っていますね。
逆に、現在の小さな月見団子を見た江戸の人が驚くことは間違いありません。
このように、月見団子は満月の象徴でありながら、地域や時代によって多様な表情を見せる、日本の秋の風物詩の一つです。
すすきの意味

秋の七草の一つであるすすきは、昔から日本の暮らしに欠かせない植物でした。屋根葺きの材料に使われたり、炭俵を編んだりと様々な利用法があり、ただの草とは違う特別な資源でした。
また、すすきは霊力を持つ植物としても信じられてきました。お正月の門松が神様の依代とされるように、収穫期のすすきにも月の神様が宿ると考えられていたのです。
本来は稲穂が月の神様の依代ですが、十五夜の頃はまだ稲穂が実っていないため、その代わりに形が似ているすすきをお供えとして用いました。
さらに、すすきの鋭い切り口は悪霊や災いを遠ざける魔除けの力があるといわれ、収穫物を守り、翌年の豊作を願う意味も込められています。
そのため、お月見が終わったあとは、すすきを軒先に吊るして魔除けとする地域もあります。
すすきは身近な場所に生い茂っており、道端や川の土手、畑の隅、線路沿いなどで見つけられます。
秋のこの時期には、スーパーや花屋でも立派に売られていることも多いです。
この秋はぜひ、すすきを探しに近所を歩いてみてはいかがでしょうか。
秋の風とともに、古くからの自然の恵みと神秘を感じることができるでしょう。
里芋の意味

十五夜のお月見で特に重要なお供え物に「里芋」があります。
里芋は、かつて日本人の主食だった歴史を持ち、私たちの先祖が長く食べ続けてきた大切な食材です。
昔から「里芋は十五夜までに育つ」と言われ、田畑で採れたばかりの初物として、里芋は月の神様への最高のお供え物とされてきました。
そのため、十五夜は別名「芋名月」とも呼ばれています。
江戸時代には、十五夜に里芋の煮物を食べる風習が広く一般的でした。

このほかにも枝豆や栗、季節の果物など、秋の収穫物をお供えします。
こうしたお供え物は、月を愛でるという行為だけでなく、秋の豊かな恵みと収穫に感謝する日本の伝統的な収穫祭の側面を持っているのです。
十五夜とうさぎの関係

西洋の満月の夜は、オオカミ男が吠え、ドラキュラ伯爵が闊歩するという物騒なイメージですが、日本の月はまったく異なります。
そこには、うさぎが餅をつき、かぐや姫の故郷がある、実に風雅で幻想的な世界が広がっています。
この「月のうさぎ」の伝説は決して日本だけのものではありません。
インド、中国、ヨーロッパ、さらにはアメリカのインディアンの伝承にまで及び、古代インド発祥の物語が中国を経て日本に伝わったと言われています。
中国の昔話では、月のうさぎは不老長寿の妙薬を作るために月桂樹の葉を臼でついており、その影が月に見えると伝えられています。
日本ではそれが稲作と結びつき、餅つきの風習として受け継がれました。

1950年代、宇宙船が月に到達し、歩く人影をテレビで見る時代が訪れましたが、科学の発展によって月の表情は思いのほか単調だとわかりました。
2012年には、月のうさぎの形が巨大隕石の衝突でできた地形であることが衛星の観測で証明されました。
川柳作家・西出楓楽の一句に、「太陽と未来 月とは過去語る」という言葉があります。
科学が進歩し、神話や空想が消え去る時代になっても、先人たちが愛した神秘的な月の世界は、これからも私たちの心に意味を持ち続けるでしょう。
日本の月にまつわる美しくも深い物語は、科学と伝説が交錯する舞台で今なお生きています。
お団子を盗っても許される?
出典;https://www.townnews.co.jp
地域に伝わるユニークな風習のひとつに、「お団子盗み」や「お月見泥棒」と呼ばれる行事があります。
これは、子どもたちが長い竿の先に針金や針をつけて、お月見の供え物であるお団子を突き刺して盗むというものです。
昔から子どもたちは「月からの使い」と考えられ、中秋の名月の日だけはこの行為が許されていました。
月の神様がすすきを伝って地上に降りてきて、お団子を持ち帰るという伝承もあり、この盗みは「神様がお供えを受け取る」という吉兆の証とされていたのです。
そのため、お団子を盗まれた家は豊作や幸運に恵まれると考えられ、わざと盗みやすい場所にお供え物を置く習慣もありました。
現在も、子どもたちが「お月見ください!」「お月見泥棒でーす!」と声をかけながら家々を回り、お菓子をもらう地域があります。まるで日本版ハロウィンのようなほほえましい風習です。
この風習は千葉県、愛知県、三重県、奈良県、茨城県、福島県、大分県などの農村地域を中心に伝わってきましたが、近年は徐々に少なくなり、今では希少な地域文化となっています。
時代を超え、子どもたちと月の神様をつなぐ大切な祭りのひとつとして、今なお人々の心に生き続けているのです。
お月見いろいろ!十六夜・十三夜とは
十五夜は、一年の中で最も美しい月夜として知られ、多くの人がお月見といえばまずこの夜を思い浮かべるのではないでしょうか。
しかしながら、お月見は十五夜だけではありません。
ここでは、少し忘れられかけているもう一つの月見、「十六夜」と「十三夜」についてご紹介します。
十六夜
十六夜、あるいは「いざよい」と呼ばれる夜は、新月から数えて16日目、つまり十五夜の翌日の夜のことを指します。
2025年の十六夜は10月7日(火)にあたります。
「いざよい」とは古語で「ためらう」を意味し、十五夜の月に比べて月が空に昇るのが約30分〜40分遅く、まるで月がためらうかのように見えることからこの名がつきました。
この美しい言葉「十六夜」は、秋の季語としても古くから和歌や俳句に詠まれ、日本の文学や芸術に深い趣を与えてきました。
十六夜自体にお月見の特別な風習はありませんが、十五夜の翌日ということで、まだ美しい月を楽しめる夜です。
もし十五夜に天候などで月を拝めなかったとしても、がっかりすることはありません。
そんな時は、ぜひ十六夜の月をじっくりと味わってみてはいかがでしょうか。
十三夜
「十五夜」の約1か月後、旧暦9月13日にも「十三夜」という特別な月見の日があります。
十三夜は十五夜に次いで美しい月とされ、2025年は11月2日(日)にあたります。
昔から十五夜と十三夜のどちらか一方だけを楽しむのは「片見月」と呼ばれ縁起が悪いとされてきたため、両方お供えをするのが習わしでした。
十三夜は「栗名月」や「豆名月」とも呼ばれ、これは秋の収穫の栗や枝豆がちょうど旬を迎えることに由来します。
十五夜が「芋名月」とも呼ばれるのと同様に、お供え物に旬の実りをそろえることが伝統となっています。
今年の十三夜の詳細については、記事で詳しくご紹介していますので、ぜひご覧ください。
【関連記事】
月見団子レシピ
今年のお月見には、簡単で美味しい月見団子作りにチャレンジしてみませんか。
手軽な材料で作れるレシピをご紹介しますので、ぜひ自宅でお団子を手作りして、秋の風情を存分に楽しんでください。
基本の月見団子
4ステップでできる、基本の月見団子の作り方です。

- ボウルに白玉粉と絹ごし豆腐を入れ、手でこねます。
- 耳たぶくらいの固さになったら15等分にして、丸めます。
- 大鍋に湯を沸かし、沸騰したら【2】を入れます。
浮いてきて3分程ゆでたら、冷水にとります。 - お団子の水けをきって、器に盛り付けて完成です。
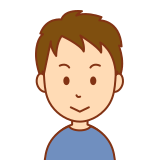
完成したら、きな粉やあんこなどお好みのトッピングで食べよう!
みたらしあんのレシピ
お団子に合う美味しい「みたらしあん」のレシピをご紹介します。

- フライパンに全ての材料を入れ、弱火にかけます。
- 加熱しながら、ヘラでよくかき混ぜます。
- とろみが出て、あんに透明感が出たら完成です。
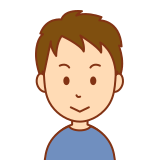
あんが冷めて固まっても、レンジで少し温めれば復活するよ。
折り紙でお月見を楽しもう
ここでは小さなお子様が喜びそうな、かつ作りやすい折り紙の製作をご紹介します。
ぜひお月見する際には、一緒に飾ってみてください。
三方(月見団子)
月見団子を乗せる台「三方」を作ります。
お団子は、100均の手芸用品コーナーに売っている「デコレーションボール」を乗せましょう。
すすき
お月見には必須のすすき。魔除けの意味を持つ大事なアイテムですね。
折り紙のほか、ボンド・はさみ・定規・カッターをご用意ください。
作ったすすきは、花瓶を作って挿すと素敵です。
その花瓶の作り方はこちらです。
うさぎ
月を眺めているような、上を向いているうさぎを選びました。
お月見らしさが増しますね。ぜひチャレンジしてみて下さい。
折り紙でお月見飾りを完成させた達成感に浸ったら、次はその作品をディスプレイして眺める楽しみを味わいましょう。
手作りの温もりあふれるお月見飾りと共に過ごす時間は、お子さまの心に優しく刻まれ、やがて懐かしい思い出となるはずです。
家族みんなで大切な十五夜のお月見を楽しみ、秋の夜長に心豊かなひとときを共有してくださいね!
おわりに
いかがでしたでしょうか。
月を眺めていると、不思議なパワーをもらえる気がしますね。
かつて夜の灯火が普及するまでの月光の意味は、現代を生きる私たちにははかりしれないほど大きなものだったに違いありません。
2025年の十五夜は10月6日です。
ぜひお供え物をして、美しい月夜を満喫しましょう。









