新年を迎えたお正月には、みんなでゆっくり1年の疲れを癒したいですね。
家族でおせちを囲む楽しいひとときに、「お正月の食文化」の由来などの豆知識を披露して盛り上げてみませんか?
今回は、お正月料理について、家族みんなが笑顔になるようなとっておきな小話をご紹介します。
おせち料理とは?

日本人は昔から、食べ物を神様に捧げ、感謝し、祈るという風習を大切に守ってきました。
お正月のおせち料理やお雑煮は、その代表なものといえます。
お正月におせちを食べる意味は、主に2つ。
新たな年を迎える祝いの形として、日本人がいつまでも大切にしたいお正月の風景です。
おせちに不可欠な3種「三つ肴」とは?

『三つ肴』または『祝い肴』という、おせち料理に欠かせない、代表的な3つの料理があります。
全国的に黒豆と数の子は共通ですが、3つめの料理は関東ではごまめ、関西ではたたきごぼうです。
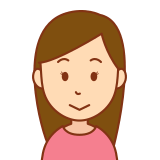
おせちを用意できなくても、代表としてこの「三つ肴」を用意するだけでもOKということだよ!
正式には何段重ね?
お節料理の重箱は、伝統的には4段重ねです。
これは、完全を表す「3」という数字に、さらにアンコールとして「1」を足したものです。
例えば「特急」の上に「超特急」があるのと同じ発想によるものです。
重箱に入れる料理は何?
それぞれのお重には、このような料理を詰めていきます。
| 一の重 (一番上) |
「祝い肴」といって、三つ肴(おせちに欠かせない料理)を入れる。 | 関東:黒豆、数の子、ごまめ 関西:黒豆、数の子、たたきごぼう |
| 二の重 | 「口取り」といって、いわばオードブル。 | 伊達巻、金団、かまぼこ、なますなど |
| 三の重 | 「焼き物」海の幸を焼いたもの。 | 海老、鯛、鮑など |
| 与の重 | 「煮物」山の幸を煮たもの。 | 里芋、八つ頭、蓮根など |
四段目については、四が「死」を連想させて縁起が悪いことから「与の重」と呼ばれています。
お重に入れる品数は、吉数とされる奇数が良いとされています。
おせちの中身の意味や願いとは?

おせちには、それぞれの料理におめでたい意味やいわれがあります。
その地域、家庭によってさまざまですが、ここではよく知られているものをご紹介します。
黒豆
黒は「魔除けの色」であり、1年の邪気を祓って不老長寿をもたらすとされています。
また語呂合わせで「まめ」に暮らせるように、という願いが込められています。
かずのこ
ニシンの卵から「二親」とかけ、子孫繁栄に恵まれるようにと願っています。
ごまめ(田作り)
小魚を田んぼの肥料にしていたことから、豊作祈願の意味が込められています。
たたきごぼう
豊作だった年に飛んでくるとされる瑞鳥を表していて、今年の豊作と息災の願いが込められています。
こぶまき
「よろこぶ」の語呂合わせで、養老昆布とも読み、長寿への願いを込められています。
だて巻き
昔の書物の巻物のイメージから知性を表し、知識が増える。さらに卵は子孫繁栄の象徴とされています。
紅白なます
神聖な「白」、慶事の色「紅」で、おめでたさを表しています。
また、お祝いの水引に見立てられているとされ、家族の平和への願いが込められています。
海老
長いひげを生やし、腰が曲がるまで長生きしてほしいという願いが込められています。
紅白かまぼこ
日の出を象徴する半月の形と、神聖な「白」慶事の色「紅」で、おめでたさを表しています。
里芋
親芋にたくさんの小芋がつくことから子孫繁栄の意味があります。
蓮根
穴がたくさん開いて向こうが見えることから「将来の見通しがきく」という縁起をかついでいます。
栗きんとん
小判のように黄金色に輝いていることから、商売繁盛の願いが込められています。

一つ一つ、祈りの意味を知った上で食べると、御利益がありそうだね!
今年はみんなのお願いごとに合わせて選んで食べるのも、楽しいのではないでしょうか。
デパートで買うおせちの相場は?
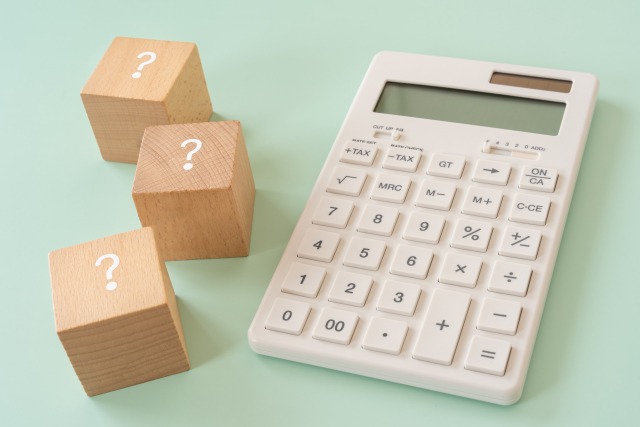
各デパートでは、だいたい11月下旬からおせち料理の受け付けが始まります。
新年にふさわしく豪華で、本格的な料亭の味を楽しめますので、利用してみても良いでしょう。
そこで気になるのが、どのくらいの値段で選ばれているのでしょうか?
一番人気は10,000〜20,000円
2〜3人用までのサイズが中心となります。
中でも15,000円前後の価格が人気のようです。
ファミリー用で人気は20,000〜30,000円
3〜4人用までのサイズで、品数やボリュームもあります。
有名料亭監修で人気は30,000〜40,000円
4人用〜のサイズが中心で、有名料亭やスターシェフ監修の豪華なおせちです。
こだわりの高級食材を使い、老舗ならではの技が生かした特別なおせちです。
おせち通販を利用する際のポイント
冷蔵・冷凍タイプの確認
おせちには冷蔵タイプのものと、冷凍タイプのものがあります。
冷蔵タイプのものは賞味期限が短く、こちらで盛り付けする場合があります。
しかし解凍する手間がありませんので、すぐに食べるなら冷蔵が良いですね。
冷凍タイプは長期保存ができ、彩りよく盛り付けされていますので、そのまま食卓に上げることができます。
近年では、冷凍技術の進化によって食材の鮮度や風味ほとんど落とさず、美味しく食べられるようになっています。
ですので、冷蔵か冷凍にするか、あなたのスタイルに合ったおせちを選ぶと良いでしょう。
食材の産地の記載
おせちの製造地は国内ですが、食材も国産であるとは限りません。
国産品にこだわりたい方はしっかりと確認しましょう。
到着日の確認
年末年始は配送業者がもっとも忙しい時期ですので、通常よりも配送が遅れることもあります。
冷凍タイプのおせちは解凍する時間が必要ですので、余裕を持って注文するのはもちろん、日時指定についてもチェックしておきましょう。
おすすめ百貨店のおせち通販

百貨店のおせちには、長年培われた味、品質に見合った価格、そして配送システムなど、百貨店ならではの安心と信頼感があります。
有名百貨店の包装紙で届くおせちは、遠くに離れているご家族へのプレゼントにもすごく喜ばれるので、おすすめです。
大丸・松坂屋
人気の料理店やホテルが手がけた本格的なおせちが、お手頃価格で味わえることでとても人気です。
定番のおせちから、大丸・松坂屋ならではの豪華な顔ぶれが話題となっている特別企画のおせちも用意され、毎年楽しませてくれています。
近鉄百貨店
近鉄百貨店は、毎年おせちにかなり力を入れていることで有名です。
ほかのデパートと違う大きな魅力は、とにかく品揃えが豊富なことと、「近鉄オリジナルおせち」があることです。
なかでも近鉄名物の近鉄電車おせちが毎年大人気で、毎年さまざまな電車おせちがお目見えします。
今年はどんなユニークなコラボを見せてくれるのか楽しみですね。
お雑煮の意味とは?

『お雑煮』の語源は、色々な具材を「雑ぜて煮合わせた」ことからきています。
本来は、大晦日の夜に年神様にお供えした餅や野菜を元日に下げ、一家の長が元旦に初めて汲んだ若水で煮て、みんなで食べていたものでした。
人々は神さまと同じものを食べることで、神さまから力を授かると考えていました。
つまり、お雑煮を食べることは、神さまと一緒に食事をするという大事な儀式でもあったわけです。
昔はなかなか餅米は高価でが手に入らなかったため、餅の代わりに里芋を入れていたそうです。
餅が手に入るようになったのは江戸時代に入ってからです。
一年の豊作や家内安全を願いながら食べられてきたそうですよ。
それから現代のように、新年の最初にお雑煮を食べる風習が継承されてきたのです。
個性あふれるお雑煮
あなたのお家では、どんなお雑煮を食べていますか?
お雑煮は日本各地域によって、本当に多彩な種類があります。
「お雑煮の好みを聞けばその人の出身地がわかる」なんて言葉もあります。
- お餅は丸か、四角か。
- お餅は焼くのか、生のままか。
- 汁は、すまし汁か、味噌仕立てか。
- 具は魚が入るのか、鶏肉か、それとも野菜だけか。
などなど・・・。
家に年神様をお迎えするために、地場の産物をお供えしたお雑煮。
だから中の具も、その地域性や風土が強く押し出されているのです。
地域別にみるお雑煮文化圏
関東から東の地域では、角餅を一度焼いてからすまし汁。
関西から西の地域では、丸餅を白みそ仕立ての汁に入れるのが多いようです。
また、香川や愛媛では「あんこの入った餅」を使用したり、岩手では、くるみ雑煮という「甘いくるみだれに雑煮の餅をつけて食べる」というものもあるそうです。
そのほか東北、中国地方、九州の一部では「小豆雑煮」などもあるそうですよ。
これほどまでに個性豊かな食べ方で、お雑煮は日本全国で楽しまれているのがわかりますね!
おわりに
最近では、おせち料理といっても関心を持つ人が少なくなり、お正月に食さない家庭も増えているようですね。
しかしお正月料理に込められた深い歴史やルーツが知ると、炬燵を囲んで家族団欒を楽しみ、家族の幸せを神さまに託す祖先たちの想いを感じ取ることができますね。
ぜひ新年の特別な日は、みんなでおせち料理やお雑煮を囲みながら、私たち祖先の尊い足跡に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。







