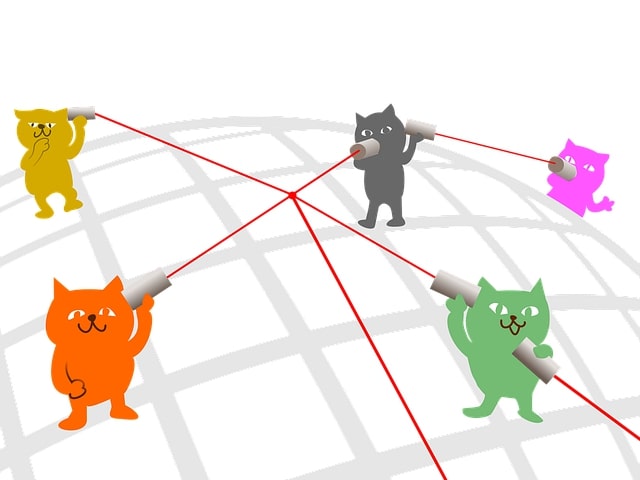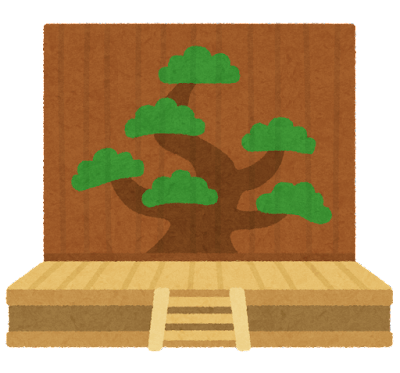歌舞伎役者は、歌舞伎の舞台だけでなく、テレビ番組やCM、YouTube、SNSの発信などでも活躍し、とても人気がありますよね。
ですが歌舞伎役者には、私たちが感じる人気とは別に、「歌舞伎界の内部に序列」が存在していることは、ご存知でしたか?
今回は、そんな歌舞伎界の格付け・序列についてご紹介していきたいと思います。
歌舞伎の屋号とは?

歌舞伎役者には、名前の他に、『〇〇屋』という、屋号があります。
例えば、市川海老蔵さんの屋号は、『成田屋』です。
歌舞伎役者に対し、「成田屋ぁ~」、「音羽屋っ!」といった掛け声を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。これが、屋号です。
「〇〇屋」というと、なんだかお店屋さんみたいですよね?
実はその通りで、元々実家が商売をやっていた歌舞伎役者が、出演報酬だけでは食べていけず、副業としてお店を出して「〇〇屋」と屋号を名乗りました。
それが、いわゆる歌舞伎の屋号のもとになったと言われています。
もう少し詳しく見ていきましょう。
歌舞伎の屋号の由来

江戸時代には、今では考えられないほどの身分差別があり、武士以外は苗字を持つことが許されませんでした。
そこで商人や農民が、苗字の代わりに、家ごとに名乗れる呼び名を作っていたのです。それが、「屋号」でした。
有名なものを挙げると、「紀伊国屋」「越後屋」、「鍛冶屋」、「紺屋」、「油屋」などなど、たくさん挙げられます。
歌舞伎役者もそうでした。特に彼らは、江戸時代初期ごろまでは、河原者(ホームレスのような生活をしていた人たち)と呼ばれて、当時は社会的に最も差別された扱いでした。
やがて彼らの人気が少しづつ高まると、幕府によって商人と同じように表通りに住むことが認められるようになりました。
しかし、だからと言ってすぐに表通りに住むのは気が引けていた彼らは、小さなお店を出して「〇〇屋」と屋号を名乗りました。
商人としての実態を作っておけば、身分上「商人」と名乗れて堂々と表通りに住めるし、商売をすることで副収入も得られるからです。
すると他の役者も「それはいいアイデアだ」ということで真似をし、それぞれ屋号を作っては、お店を出していきました。
お店を持った役者たちは、お互いのことを「〇〇屋」と屋号で呼び合うようになり、これが、民衆の間でも彼らの屋号が広まっていきました。
そうしてようやく歌舞伎でも、役者としての屋号で呼べるようになったのです。
歌舞伎役者にとって屋号は、看板ともいえる大事なものとなっていきました。
河原者と呼ばれ、蔑まれた立場だった歌舞伎役者は、やがて市民権を得て、今では日本の伝統文化として認められていったのです!
屋号の種類は多い!
歌舞伎の屋号は、実は意外と多く、100種類以上あると言われています!
基本的に、その一族でずっと同じ屋号を使い続けます。
屋号が、そのまま家柄を表すのです。
歌舞伎の家柄(屋号)にはランクがある

歌舞伎の世界には、序列がしっかりとあります。
ただ、歌舞伎役者の家系図はとても複雑で、それを紐解いていくと、家の存続のために別の家から養子をもらったりと、元をたどれば全員が親戚にもなりかねない世界です。
ですから、一般的にその格付けは分かりにくくなっています。
ただし、屋号の歴史が古ければ古いほど、重く見られるという事実があります。
ランクが上位になる条件はこのようなものです。
つまり、屋号の歴史が古ければ古いほど、そして貢献度が高いほど、ランクは上位ということになります。
では早速、江戸時代から続く、歌舞伎界で最も「格が高いとされる屋号」と、特に有名で格の高い12屋号をご紹介します。
最上位!
成田屋
【代表的な名跡】
市川團十郎・市川海老蔵・市川新之助 など
歌舞伎の世界で 一番格が高い家柄 と言われ、特別な存在とされているのが『成田屋』です。
みなさんがテレビなどでよく見ていた市川海老蔵さん。その屋号(家の呼び名)が成田屋です。
海老蔵さんは2022年に正式に 『十三代 市川團十郎白猿』 を襲名し、歌舞伎界の中心的存在となりました。
そもそも初代「市川團十郎」は、江戸歌舞伎の始まりを作った人で、なんと300年以上前から続く大名跡です。
彼は、自分で芝居小屋をつくりお客を集めるスタイルを確立し、さらに「荒事」と呼ばれる、力強く華やかな演技を打ち出しました。
この迫力ある芸は江戸の人々を大いに熱狂させ、「江戸歌舞伎といえば成田屋」と言われるまでになったのです。
そのため、今でも成田屋は「江戸歌舞伎の代表」として特別に重んじられています。
特に「市川團十郎」という名跡は、歌舞伎界全体を支える 大黒柱 と呼ばれる、最も権威ある名前です。
現在、その名を継いだ 市川團十郎白猿丈 は、伝統を守りつつ新しい取り組みにも挑み、歌舞伎の未来を切り開く存在として大きな注目を集めています。
成田屋以外の、江戸時代から続く名門
成田屋は別格の最上位。では、それ以外の代表的な家柄と屋号、主な役者は誰なのでしょう?
いくつか確認してみましょう!
音羽屋
【代表的な名跡】
尾上菊五郎・尾上菊之助・尾上松也 など
成田屋と並んで江戸歌舞伎の中心的存在となったのが、この『音羽屋』です。
もともと音羽屋は、京都の芝居小屋「都万太夫座」で観客の案内や飲食の提供を行っていた一座でしたが、大坂での公演の際に成田屋・市川團十郎にその才能を見出され、江戸に拠点を移すことになりました。
初代・尾上菊五郎の父、半平は清水寺の近くで生まれ、その境内にある「音羽の滝」にあやかって「音羽屋半平」と名乗ったのが、屋号「音羽屋」の始まりとされています。
音羽屋の芸風は、粋でいなせな江戸っ子気質が持ち味。
『弁天小僧』のような世話物(人情や市井を描く芝居)や、怪談を題材にした舞踊劇などを得意とし、今もなお観客を魅了し続けています。
高麗屋
【代表的な名跡】
松本白鸚・松本幸四郎・市川染五郎など
松本幸四郎の屋号『高麗屋』は、初代・松本幸四郎が若い頃に江戸・神田の「高麗屋」という店で奉公をしていたことに由来します。
歌舞伎界で最も格式の高い「成田屋(市川團十郎家)」とは非常に縁が深く、跡継ぎが不在のときには高麗屋から養子を出すなど、師弟関係を超えた強い結びつきが続いてきました。
つまり、今は「高麗屋」の役者として活躍していても、状況によっては成田屋に養子入りして「市川團十郎」を名乗る可能性もあり得るわけです。
実際に、七代目松本幸四郎の長男が成田屋へ養子に入り、のちに十一代目市川團十郎となりました。
そして2025年現在、その十一代目の長男は十三代目市川團十郎白猿として大名跡を継承しており、その息子もすでに舞台に立ち“次世代の團十郎候補”として注目されています。
中村屋
【代表的な名跡】
中村勘三郎・中村勘九郎・中村七之助 など
歌舞伎の名跡として広く知られる『中村屋』。
テレビの密着番組などで家族の様子が紹介されることも多く、一般にもなじみ深い名前になっています。
実はこの「中村屋」という屋号を正式に名乗るようになったのは 十七代目中村勘三郎(1935年生〜2012年没) の代からです。
もとをたどると、江戸時代に歌舞伎を上演していた『江戸三座(中村座、市村座、森田座)』のひとつで、最も古い芝居小屋だった 「中村座」 が由来になっています。
初代・中村勘三郎は、もともと「柏屋」という屋号を使っていた一座の座元(経営者)・猿若勘三郎が名乗ったのが始まりです。ただし明治時代に一度その系統は途絶えてしまいました。
その後、戦後の昭和25年(1950年)に十七代目中村勘三郎を襲名した役者が現れ、このときに屋号が「中村屋」と改められ、今日まで続いています。
大和屋
【代表的な名跡】
坂東三津五郎・坂東八十助・坂東玉三郎 など
大和屋は、歌舞伎の名跡であると同時に、「日本舞踊の名門」として広く知られています。
初代・坂東三津五郎が養子に入った坂東三八の実家が「大和屋」という商売をしていたことから、屋号も『大和屋」』となりました。
この家柄は、歌舞伎だけでなく日本舞踊界においても重要な存在で、日本舞踊坂東流の家元として伝統の継承と発展に大きな役割を果たし続けています。
成駒屋
【代表的な名跡】
中村歌右衛門・中村芝翫・中村橋之助 など
四代目市川團十郎から、「成駒柄」の着物が贈られたことに感謝した、四代目中村歌右衛門が、それまでの屋号だった「加賀屋」を改め、「成駒屋」にしたのが由来です。
八代目中村芝翫さんの妻はタレントの三田寛子さんで、その3人の息子さんは「成駒屋3兄弟」と呼ばれ、現在歌舞伎役者として活躍中です。
松嶋屋
【代表的な名跡】
片岡仁左衛門・片岡愛之助・片岡孝太郎 など
15代続く大名跡「片岡仁左衛門」を筆頭とする『松嶋屋』。
大阪の歌舞伎を代表する一門で、関西中心に活躍しています。
屋号『松嶋屋』の由来は不詳ということで、残念ながらなぜこの名前になったのかは誰にもわかりません。
ちなみに、メディアでの活躍で知名度の高い片岡愛之助さんですが、彼は二代目片岡秀太郎の養子であり、もとは一般家庭の出身です。
そのため「愛之助」の名前の格は低く、明治座などで座頭は務めていますが、歌舞伎座では大きな役はなかなか回ってきません。
現在の仁左衛門さんには、長男・片岡孝太郎、孫・片岡千之助がいるので、大名跡「片岡仁左衛門」を継ぐことは難しいとされています。
しかし2010年に市川海老蔵さんが顔にけがを負った事件で、彼の代役として、たった3日間の稽古で『吉例顔見世興行』を見事に演じ切り、喝采を浴びました。
これが愛之助さんが一躍注目を浴びたきっかけとなり、その数年後には、ドラマ『半沢直樹』でのヒール役で好演したことで大ブレークを果たし、仕事の幅が一気に広がっています。
人気と実力は抜群にありますので、お客さんを集める力は十分にあります。
歌舞伎役者の格付けはどうやって見分けるの?
出典;https://userdisk.webry.biglobe.ne.jp
歌舞伎の舞台では、主役級を演じるのは「格が高い家柄の役者」と決まっていて、ほかは脇役を演じるのが伝統となっています。
ですので、格の違いは、歌舞伎で演じる役を見ればわかります。
格の高い家柄の役者は主役を演じるので、劇場の看板では、最初や上の方など、目立つ場所に名前が掲げられます。
格の高くない家柄の役者は、歌舞伎座では主役を演じる事はありませんが、地方公演などで主役を演じる事はあります。
とはいえ、いくら格が高い家柄の役者であっても、実力が伴わない場合は主役を与えられることはなく、最近では、「家柄の伝統」に加えて「本人の力量や努力」も配役を決めるうえで重視されるようになっています。
おわりに
歌舞伎の創始者と言われる、市川團十郎家(成田屋)は最上位となり、その他は、成田屋と同じ様に江戸時代から続く家柄は、「名門」と言われます。
現在、歌舞伎役者は300名ほどいるということなので、歌舞伎座などのような大きな劇場の本公演に出演できるのは、ほんの一握りということです。
光があるからこそ、影もあるのですね。
身分差別から、日本を代表する伝統芸能まで上り詰めた背景には、芸を貫き、極限まで磨いてきたからこそ、多くの人々に支持され続けてきたのかもしれませんね!